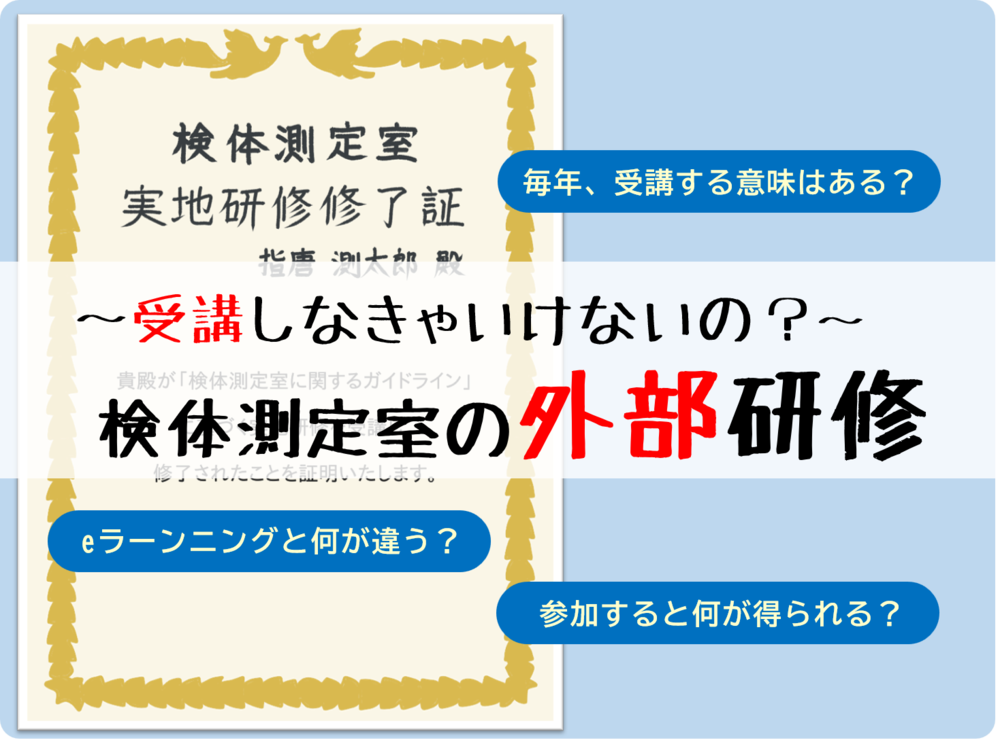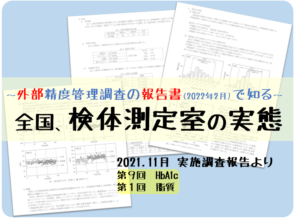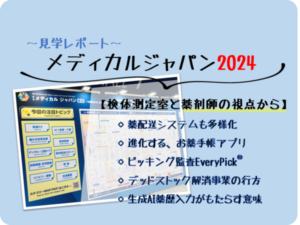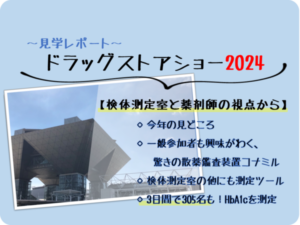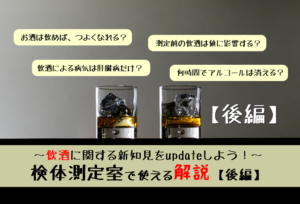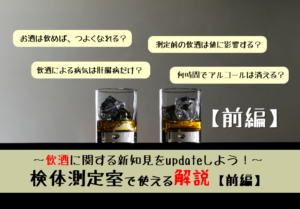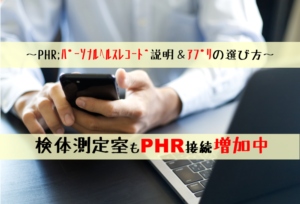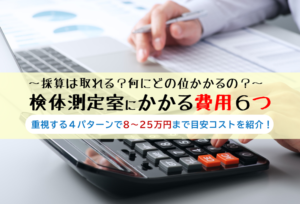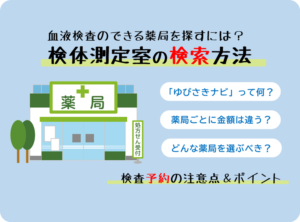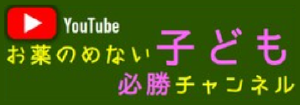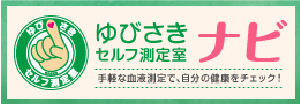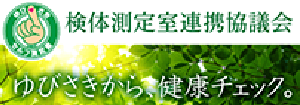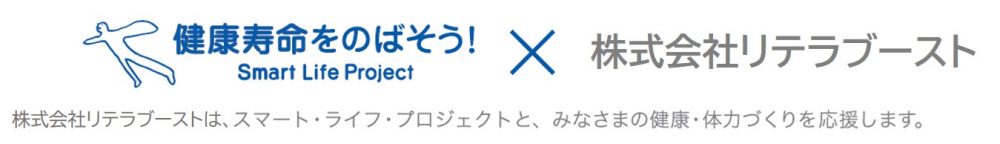検体測定室の「外部研修」は、社内や事業所内で自主的におこなう「内部研修」とちがい、さまざまな情報を得ることのできる貴重な機会です。ガイドラインでは、「内部研修に留まることなく、……外部研修を受講させる(抜粋)」という明記も。ここでは、検体測定室の外部研修に参加するメリットや必要性について紹介します。この研修をうまく活用し、運営責任者だけでなく測定従事者のスタッフ全員で、より良い運用へとつなげましょう。
外部研修の必要性
検体測定室では「検体測定室に関するガイドライン1)」(以降、ガイドラインと略)にしたがい、内部研修とは別に外部研修を受けることが必要です。ただ、参加における頻度や実施する機関については明記されていません。まずは、「内部研修」と「外部研修」の違いについて理解しておきましょう。
「内部研修」はガイドラインにおいて詳しい記載がないものの、その事業所(検体測定室)ごとに日常業務で必要な情報周知に関する研修と捉えることもできます。例えば、測定業務や必要な物品に関する取り扱い、受検者さんに対する支援のあり方、緊急時のスムーズな対応など細部にわたって周知することが大切です。
対して「外部研修」は、「内部研修」の上流にある研修要綱の大元といっても過言ではありません。その内容は、関係法令、精度管理、衛生管理、個人情報保護など。なかには検体測定室だけでなく、多岐にわたる業種で基盤となっている情報も含まれます。これらは随時、情勢や法改正に伴い見直されているため、短時間で効率よくこうした情報を得るには外部研修を活用するのがおすすめです。
1) 外部研修で扱われる情報とは?
『 運営責任者は、業務に従事する者に、内部研修に留まることなく、関係法令、精度管理、衛生管理、個人情報保護等について必要な外部研修を受講させるものとする。 』
検体測定室に関するガイドライン(抜粋)平成26年4月9日付医政発0409第4号厚生労働省医政局長通知 第2‐17
「研修」
どこで受講できる?
外部研修は2024年5月の時点で、検体測定室 連携協議会 が年に1回、11月14日の世界糖尿病デー※にあわせて開催しています。その開催の形態は感染症予防にも配慮した、東京大学 医学部 鉄門記念講堂でのリアル参加とオンライン(zoom)参加の、いわゆる”ハイブリット開催”。検体測定室に興味のある人なら運営責任者でなくても参加でき、情報を得ることが可能です※。
現に、検体測定室の運営者だけでなく、糖尿病や脂質異常症など生活習慣病の発症予防に取り組む製薬企業や一般社団法人、メディア関係者、医療機器製造業者など多くの分野から参加者が集います。費用は検体測定室連携協議会の会員については無料ですが、非会員でも参加費用(数千円)を支払うことで受講可能です。
※世界糖尿病デー:糖尿病を正しく理解して予防や療養、偏見などについて啓発活動を呼びかける日として国際的に11月14日を定めている。
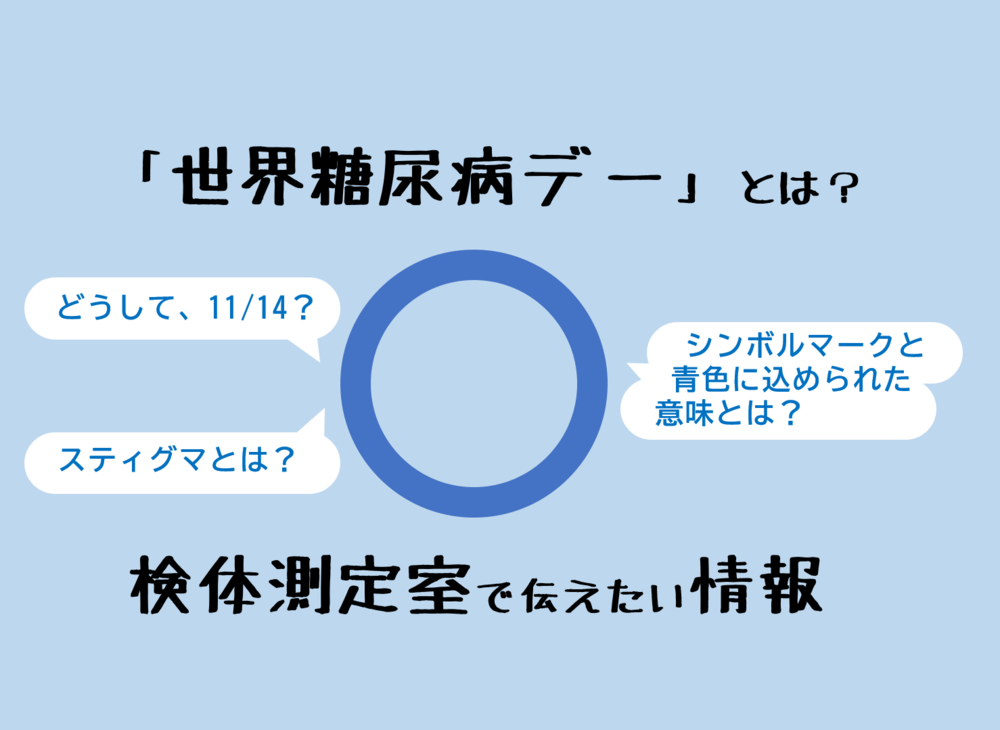
※検体測定室連携協議会の主催する外部研修について、非会員が参加する場合は有料です。詳しくは、検体測定室連携協議会の公式サイト をご参考ください。
※当社は検体測定室連携協議会の法人正会員ですが、この記事や活動は入会の勧誘をおこなうものではありません。
受講メリットや情報内容
受講することで得られる最大のメリットは、関連団体における最新の知見や発表、ガイドラインを発行している厚生労働省の担当者による見解を得られるということでしょう。ここ2年分の、検体測定室連携協議会によって実施された外部研修「世界糖尿病デー・健康啓発セミナー」は、以下に記すような演題と登壇者で構成されていました。
とくに、質疑応答ではふだん接する機会の少ない立場の方に対し、近状やこれからの展開に関する質問を投げかけるチャンスでもあります。
また、こうした情報を積極的に得ようと参加する、企業の担当者とも接するよい機会です。例えば、測定項目を増やして提供内容の充実を図りたい場合や、自施設で持つ測定機器の他にも導入を検討する場合、解説用の資材や提供資料などの情報をより多く得たい場合は、オンライン参加よりも実際に足を運んで積極的に情報を仕入れに行くことを推奨します。
単に、ガイドラインで明記されているから仕方なく受講するのではなく、より多くの選択肢に触れる機会として活用してみてはいかがでしょうか?
| 2022年11月開催 外部研修の演題と登壇者 |
|---|
●演題①「検体測定室ガイドラインについて」 |
| 2023年11月開催 外部研修の演題と登壇者 |
|---|
●演題①「検体測定室ガイドラインについて」 |

外部研修で得られる受検者への回答
検体測定室はどうして保険がきかないの?
どの検体測定室でも同じ結果が出る?
他の項目も測れないの?
検体測定室に対して国はどんな期待をしているの?
こうした質問も受検者さんから比較的、よく受けます。これらは外部研修のなかで、その回答が得られることも。受検者さんの満足度や理解度の向上に寄与するためにも、情報の正確さや新しさ、発信元における十分な確証を備える環境で情報収集をしておくことが重要です。
また、受検者さんのなかには関心が高く、より新しく正しい情報を得たいと考えて検体測定室を利用する人もいます。一見すると、健康管理とはあまり関係がなさそうに思える質問でも、真摯に回答することで思いがけず会話が弾むこともあるでしょう。受検者さんにとっては、そうした会話も出来る場が”健康ステーション”のひとつと捉えるきっかけになるのかもしれません。
受講したあとの活用例
受講したあとは、帳簿に記録を残しておきましょう。そのほか、分かりやすい活用方法としては「研修修了証」を掲示するなどして、受検者さんに対し信頼感を与えるのも良いかもしれません。また、講義の内容を反映したポスターやチラシなどをつくり、受検者さんへ情報共有をおこなうのもひとつです。
こうした情報発信がきっかけとなって、受検者さんが「ここで質問してみようかな」という気持ちになるかもしれません。続いて、継続的な測定とともに情報のアップデートが行われていけば、より良い自己管理につながることにも寄与できるでしょう。
外部研修で得た知識は関係者だけに必要な情報ではなく、一般の人にとっても有用な情報が多く含まれています。これらを正しく発信していくことも、検体測定室に期待されている大切な役割のひとつではないでしょうか?
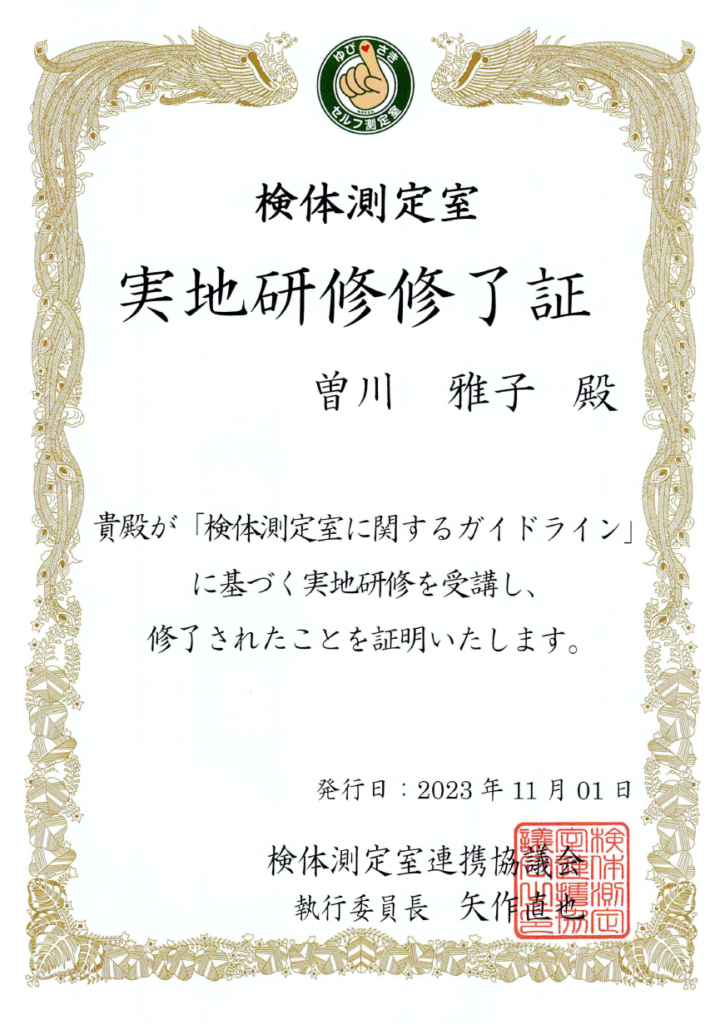
当社は毎年、
この外部研修を受講することで
最新の情報収集に努めています。
※この記事は2024年5月時点の情報です。ガイドラインの改正などにより変更が生じている際には、現状をご優先いただきますようお願いいたします。